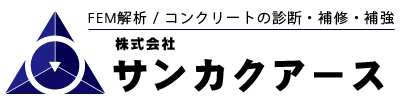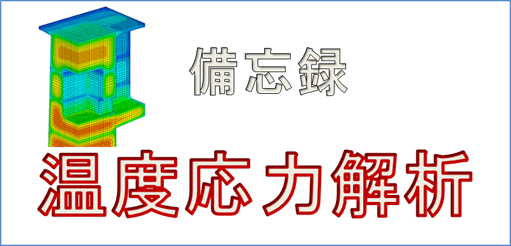①水 ②高アルカリ環境 ③反応性骨材
の3つの条件が揃った時にASRによる劣化が生じる。
☆構造物から採取したコアによる各種試験 –—————————————————–
●骨材の岩種および反応性鉱物の種類
偏光顕微鏡観察、X線回折、SEM-EDS、赤外線吸収スペクトル分析など
●アルカリシリカゲルの判定
化学成分分析、SEM-EDS
●アルカリ量
水溶性アルカリ、酸溶性アルカリなど
☆変更点【残存膨張量試験】 ———————————————————–
●JCI-DD2 ⇒ JCI-S-011
判断基準あり(阪神高速道路公団、建設省で異なる)
●カナダ法 ⇒ アルカリ溶液浸漬法
判定基準無し
●デンマーク法 ⇒ 飽和NaCl溶液浸漬法
判定基準無し
【用語】———————————————————————————————
解放膨張量 ⇒ 解放膨張率
残存膨張率 ⇒ 促進膨張率
【骨材のアルカリシリカ反応性】 ——————————————————
既設の硬化コンクリートから取り出した骨材には適用してはならない
① 化学法(JIS A1145)
②モルタルバー法(JIS A1146)
コンクリート診断士研修資料’22より
【対策】———————————————————————————————
国土交通省からの通知では下記、②③を優先している。
①無害骨材の使用
②高炉セメント・フライアッシュセメントなど混合セメントの使用
③コンクリートアルカリ総量の規制(Na2O換算 3.0kg/m3以下)
※骨材の反応性試験として、化学法・モルタルバー法が規定されている。
しかし、反応性試験で「無害」と判定されても、ASRが発生することがあるので完全なものではない。
☆細骨材が反応性骨材の場合—————————————————————–
・反応速度は速くなり、膨張量も大きくなる。
・反応性細骨材と反応性細骨材の組合せによってペシマム混合割合が変わる。
・弱材齢から非常い細かいひび割れが数多く発生する。
・反応性細骨材を含む場合、骨材寸法が大きい方が膨張は大きくなる。
・セメント量やアルカリ量のアルカリ骨材反応に及ぼす影響は反応性骨材が粗骨材のみの場合より顕著になる。