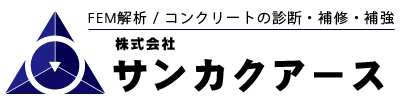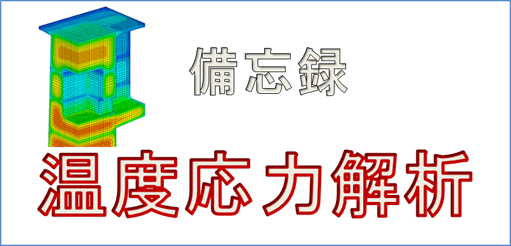【フライアッシュ】
・火力発電所など微粉炭ボイラーの燃焼排ガス中から回収された微細な石炭灰
・Ⅰ種~Ⅳ種まであるが現在、主にⅡ種相当品が使用されている
【ポゾラン反応】
・非晶質の二酸化ケイ素を主成分とし、セメントの水和反応によって生成された水酸化カルシウムと反応して緻密な硬化体組織(不溶性で安定なケイ酸カルシウム水和物)を形成する。
【フライアッシュセメント】
基本的に普通セメントを基材(混入元のセメント)としてフライアッシュを混入
特殊な場合、早強セメントとかに混入とかもあるのかもしれませんが分かりません。
※フライアッシュセメントと混和材のフライアッシュの違いは使用方法で効果、物性は同じ。生コン工場などサイロが限られている場合、サイロを確保できなかったりするため混和材としてコンクリート製造時に混ぜる。
A種(5を超え10%以下)
B種(10を超え20%以下)
C種(20を超え30%以下)
◇効果
①ボールベアリング効果によりコンクリートの流動性向上(ワーカビリティー向上)
②長期強度の増進
③乾燥収縮の減少
④アルカリ骨材反応の抑制
⑤水和熱の減少
⑥化学抵抗性の向上
【水和反応、潜在水硬性、ポゾラン反応の違い】
・いずれも生成される水和物のほとんどが珪酸カルシウム水和物(C-S-H)である。
・違いはそれぞれの物質の持っているカルシウムやシリカ、アルミなどの量の相違による反応のしやすさの程度の差
<一例>
| CaO(%) | SiO2(%) | |
|---|---|---|
| 普通セメント | 64 | 22 |
| 高炉スラグ | 42 | 34 |
| フライアッシュ | 2 | 64 |
フライアッシュは、SiO2は十分にあるが、CaOはほとんどないため自身では水硬性を示せずCaイオンはそのほとんどをセメントの水和時に生成するCa(OH)2に依存して、ポゾラン反応により硬化することとなる。高炉B種が30~60%入れられるのに対し、フライアッシュB種が10~20%程度しか入れれないのはこういったメカニズムの違いや水和活性度の違いがあると考えられる。
【細骨材としてのフライアッシュ】
・フライアッシュセメントとしてセメントに入れるフライアッシュと細骨材とみなして配合設計されるフライアッシュは基本的に同じ(Ⅱ種相当が良く使用される)
・ワーカビリティー改善のために混和材として使用される。