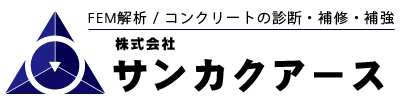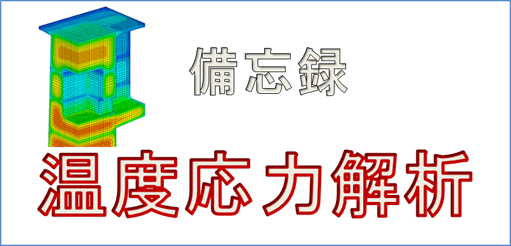【乾燥収縮のメカニズム】
乾燥収縮のメカニズムは主に以下の3つぐらいの説が有名で、その中でも①の毛細管張力説が有力なようです。詳細はまた機会があれば。。。
①毛細管張力説
②分離圧説
③表面張力説
【乾燥収縮によるひび割れ】
コンクリートのひび割れ原因として、乾燥収縮はよくあげられます。
乾燥収縮でも、発生時期、ひび割れパターンなど様々ですのでここで一度整理しておきたいと思います。
主に発生時期、ひび割れ深さ、パターン、内部拘束、外部拘束などに着目して整理してみます。
内部拘束、外部拘束など温度応力解析でよく使われますが、乾燥収縮でも同様な現象が生じていると言えます。
裏付け資料(根拠)などはそのうち追加していければと思います。これは違うといった内容や裏付け資料などございましたらご教授頂けると幸いです。
※材齢初期や中期などの時期は個人的に今回設定しただけですのでご注意ください。
●:内部拘束 △:外部拘束について記載
【材齢初期(数日〜)】〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
●急激な乾燥など養生がしっかりできていなかった場合など、数日で表面に網状のひび割れが生じます。
●ひび割れ深さは、ごく表面のみでプラスティックひび割れなどとも言われます。
【材齢中期(2,3ケ月から数年)】〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
△部材厚さの薄い建築物等(20~30㎝程度)の壁だと数ケ月で収縮し、柱等に拘束されるため貫通のひび割れが生じる。(外部拘束)
△ひび割れは拘束され引張が生じる方向に直角に発生し乾燥が収束するまで、ひび割れ幅が大きくなったり、ひび割れ本数が増える。
●部材厚が1、2mと大きくなると数年程度まで、コンクリート表面の相対湿度が小さくなり十数㎝以深は乾燥しないため、内部拘束により表面に(ひび割れ深さは浅い)ひび割れが発生。
●内部拘束によるひび割れは部材形状、部位等により変わり水平や鉛直、斜めのひび割れが生じる。
【材齢長期(十数年以降など)】〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
△部材厚さの厚い構造物の場合、40,50㎝内部まで相対湿度が20〜30%低下するまでに10数年以上要するため(ある解析条件下)、乾燥が進行する間、収縮しひび割れが発生する。
ただし、拘束体などがあり外部拘束が生じる条件下で生じるものと思われる。
40~50㎝内部の相対湿度が○%になるのに○年かかるといった資料があったはずが分からなくなってしまいました
△この場合はひび割れは、時間の経過とともにひび割れは内部に進展していくものと考えられる。
●十数年も経過すると表面から内部への湿度分布は緩やかになっていくため、内部拘束によるひび割れは収束していると思われる。(内部拘束によるひび割れは発生しなくなる)